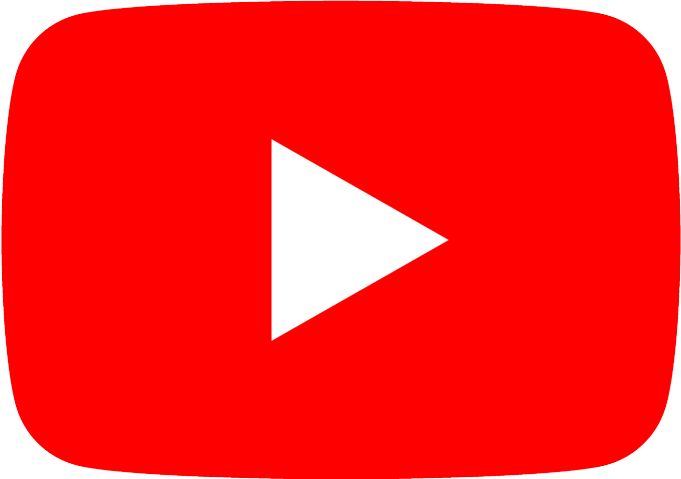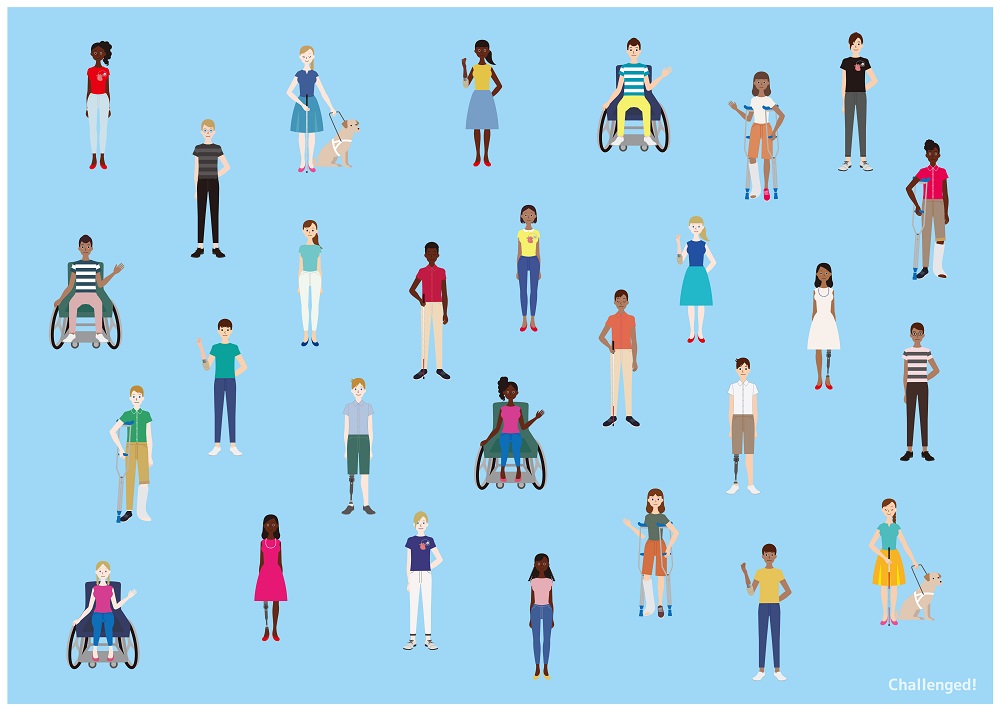ナプキン・紙おむつ問題とは
高齢化で年々大人の紙おむつ使用量が増加しており、介護者のごみ処理の負担になる、焼却すると水分を含んでいるため余計にCo2が発生し温暖化につながるなどの問題になっています。
これらの問題を解消するために、国では将来的に紙おむつを粉砕して下水に流す施策が検討されていますが、製品に含まれるマイクロプラスチックが下水を通じて海に流れ出るリスクも指摘されています。
一般にはあまり知られていませんが、子供、大人用の紙おむつ・生理用品のナプキンには、一次的マイクロプラスチックのマイクロビーズである高吸水性高分子(高分子ポリマー)が使用されています。
下水道への紙おむつ受け入れについて
年々増加する使用済み紙おむつのリサイクルはどのように処理することが理想的なのでしょうか?
紙おむつのサステナブルなリサイクルについては世界全体でも取り組みが遅れていて、ほとんどの紙おむつはごみとして捨てられ、日本では主にごみ焼却施設で燃やされています。
水分を多く含んだ使用済み紙おむつは燃えにくいため、焼却にはそれだけ多くの燃料が必要になります。また焼却すれば地球温暖化の原因になる二酸化炭素(CO₂)が発生し、紙おむつに使用される原材料として多くの森林資源も必要とするため、持続可能な仕組みを考えることが急務です。
これらのことからナプキン・紙おむつ問題をまとめると、
・ナプキン・紙おむつに含まれるマイクロプラスチックによる海洋汚染の懸念
・焼却処分による温暖化への影響
・森林資源の減少による環境への影響
などがあります。
ナプキンについては、ナプキンの代用となる吸水ショーツなどの開発も進んでいて、これまでの常識と価値観を大きく変える流れが起きています。
またコロナ禍で仕事を失うなどして収入が激減した人の中には、生理用品の購入もできなくなる「生理の貧困問題」も生じています。
ナプキンの代用となり、自分にも環境にも優しい商品が今後も開発されると思いますが、
これらの問題を解消するためのサステナブルな仕組み、循環型のリサイクル方法が求められています。
海洋プラスチック問題のポイント
便利で使いやすく、今や日常生活で欠かせない素材になっているプラスチックが、世界規模で海洋汚染の原因といわれて問題になっていることから、日本でもレジ袋が有料になり、人々はマイバッグを持参して買い物をするのが当たり前になりました。
プラスチック製のカトラリーやストローも、木製や紙製のものに変わってきており、多くの企業で改善の取り組みが始まっています。
プラスチック製品が問題なのは、プラスチックが劣化して5mm以下のサイズになる「マイクロプラスチック」と呼ばれる状態となり、分解されず海中に漂い続けて魚や貝などがエサと間違えて食べてしまうことです。
生態系にも影響し、その魚介類を私たちが摂取すると、付着した有害物質やプラスチックそのものの添加物などで私たちの健康にも悪影響を及ぼしかねないのです。
実は生活の中で私たちが意識していませんが、このマイクロプラスチックが使用されているものは意外と多くあります。
マイクロプラスチックは一次的マイクロプラスチック・二次的マイクロプラスチックに分類されます。
・一次的マイクロプラスチック (Primary microplastics)
マイクロサイズで製造されたプラスチック。洗顔料・歯磨き粉等のスクラ ブ材等に利用されているマイクロビーズ等で、排水溝等を通じて自然環境 中に流出します。
米国や英国・カナダなどをはじめ世界各国では使用が規制され、日本では、日本化粧品工業連合会が平成28 年3月に会員企業1,100社に自主規制を呼びかけて、国内主要メーカーが自主規制を行っています。微細なため、製品化された後の対策や自然環境中での回収は困難で、使用されると排水溝からそのまま川や海に流れ込みます。そのうえ環境中の毒素や汚染物資などを吸着し、食物連鎖で人間にも深刻な影響を与えるリスクが懸念されています。
・二次的マイクロプラスチック (Secondary microplastics)
大きなサイズで製造されたプラスチックが自然環境中で紫外線による劣化などで破砕・細分化されてマイクロサイズになったもので、使い捨てにされるプラスチック容器がポイ捨てされたり、屋外に放置されたりすると、雨や風によって河川から海に流れ出てしまいます。海洋に流れ出たマイクロプラスチックは、分解されるまでに数百年の歳月を要すので、廃棄物管理やリサイクル の推進を徹底し 、マイクロ化する前段階(大きなサイズ)での回収も必要です。
目に見えないプラスチック
一次的マイクロプラスチックのマイクロビーズには、紙おむつ・生理用品などの衛生用品に含まれる、高吸水性高分子(高吸水性樹脂、高分子吸収体、高分子ポリマー)といわれる特に高い水分保持性能を有するように設計されたものもあります。 
これらは意外とあまり知られていないマイクロプラスチックで、生活において必要不可欠な製品に使われていますが、便利になった反面、リスクも増加しています。
高齢化社会も加速して紙おむつの処理問題も検討されていますが、焼却処分だと温暖化も心配され、河川にゴミとして投棄されれば海洋プラスチック汚染につながります。
また女性は平均で40年間、生理を経験するといわれ、
月に1度、5日間ほど出血があり、期間中に20枚のナプキンを消費します。
試算すると、1人の女性が9,600枚のナプキンを人生で使う計算になり、
1つのナプキンに含まれるプラスチックの量は、レジ袋4枚分相当といわれ、
女性は生涯で、38,400枚ものレジ袋に値する量を消費していることになります。
必要不可欠な生理用品のマイクロプラスチック問題を解消するために、
使い捨ての製品で、高分子ポリマーが使用されているものではなく、
最近では、環境を意識して自分にも環境にも優しいエコな生理用品が注目されています。
どこまで受け入れて削減・代替用品を考えるのか、使い捨てではなくてリサイクルの仕組みが求められています。生活必需品の便利な製品を使用してはいけないではなくて、使う責任・作る責任を意識してサステナブルな循環の仕組みを考える必要があります。
理想のリサイクルとは
ナプキン・紙おむつの理想的なリサイクルとはどのようなものでしょうか?
例えば紙おむつでは、現在国で検討されているのが国土交通省の3案
A案:使用済み紙おむつから汚物を分離して洗浄し、汚物は下水に流す
B案:使用済みの紙オムツを紙オムツ処理装置で破砕し、分離した汚物は下水に流す
C案:使用済み紙オムツを紙オムツ破砕装置で破砕し、汚物とともに下水に排出する
などがありますが、いずれも洗浄や粉砕して下水に流す際にマイクロプラスチックも一緒に下水を通じて海洋に流される心配はないのでしょうか?
石油由来のマイクロプラスチックは、分解されるのに100年から200年以上の年数がかかり、これらのプランがマイクロプラスチックの懸念を検証されずに進められれば、海洋に流れ出るマイクロプラスチックをますます増加させることになります。
これに対して、企業でも紙おむつのリサイクルについて独自のリサイクル方法を考案されています。
リサイクルには様々な方法があり、回収した紙おむつを洗浄して固形燃料として利用する、または建築資材として利用する方法などさまざまな取り組みがされていますが、中でもユニ・チャームさんのリサイクルは、紙おむつをもう一度紙おむつとして使用できるようにする、「循環型リサイクル」を目指されています。
ユニ・チャームさんによると、紙おむつの不織布、吸水紙、高分子吸水材、防水材の複雑な構造に対応した特別なオゾン処理技術を開発されてリサイクルを行われています。
オゾンは酸化作用が強く、殺菌、漂白、脱臭に大きな力を発揮するとのことで、2016年から鹿児島県志布志(しぶし)市と協力して、使用済み紙おむつリサイクルを実験的に行っておられます。
その結果、温室効果ガスの排出量が、非リサイクル時と比較して87%も減り、ごみ収集量も大幅削減、森林資源の使用削減のデータを得られたことを報告されています。
今後ますます増えていく紙おむつは、森林資源の保護、温暖化防止の観点からも「循環型リサイクル」が理想なのではないでしょうか。
そしてナプキンについては、無理のない範囲で代用になる商品に置き換われば、少しでもマイクロプラスチックのリスクを減らすことができるのではないかと思います。
時代に応じて起きてくる問題を解消するために、消費者一人ひとりの価値観を変えることができる技術を、企業と社会が連携して生み出していくことが求められています。
ユニ・チャームさんのリサイクル
出典:「ユニ・チャーム紙おむつリサイクル」
関連記事:SDGsをわかりやすく!
最新記事:色のオーダーメイド「特色印刷」で、こだわりを伝えるメリットとは?はこちら
最新記事:PDFを【デジタルブック】に替えて、効果的な体験を!もうデジタルブック化はお済みですか?はこちら