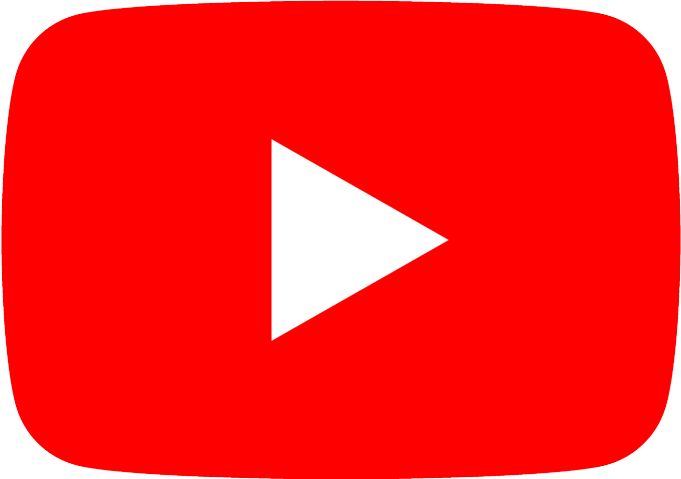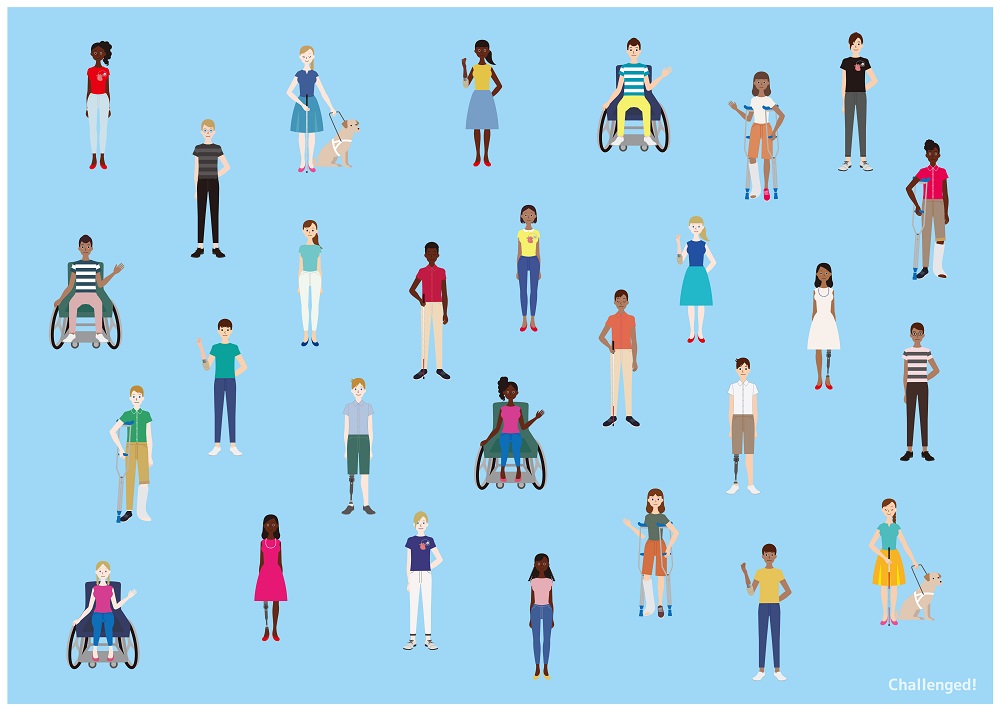フェムテックとは
FemTech(フェムテック)とは、Female(女性)とTechnology(テクノロジー)をかけあわせた造語で、女性が抱える健康の課題をテクノロジーで解決できる商品(製品)やサービスのことです。
フェムテック概念の範囲には、妊娠、不妊、避妊、授乳、育児、生理用品、産後ケア、婦人科系疾患、セクシュアル・ウェルネスなどがあり、これまでは他人に共有しづらく、どちらかというとタブー視されてきた女性の「性」の課題を可視化して解決することが、悩みを抱える女性の助けになることから、さまざまな商品が注目されています。
女性の社会進出が進み、女性の働き方やライフスタイルも変化して、女性特有の悩みについて課題解決できる商品のニーズが高まりました。
またSNSで広まった、性暴力とハラスメントの被害経験をハッシュタグ「#MeToo」をつけて投稿する#MeToo運動も影響して、女性が声をあげやすくなったこともフェムテックが認知されてきた一因です。
海外では多様な製品が開発されており、今後日本も含めた世界全体の市場規模は、2025年には5兆円規模の巨大な市場になると予想されていて、日本でもフェムテック市場の企業数は、2020年11月には97社にまで増加したと報告されています。
フェムテックの商品で注目されているのが、ナプキンやタンポン不要で、生理中を快適にしてくれる吸水ショーツ、月経カップや月経周期管理アプリなどで、さまざまな商品が開発されています。
生理の悩みを解決するアイテム
フェムテックの中には、女性が身近に感じている生理の悩みを解消するものもありますが、最近注目されている商品には、これまでの生理用品の価値観を変えるような吸水ショーツや月経カップなどがあります。
吸水ショーツ
ショーツ自体が水分を吸水するサニタリーショーツで、吸水力は商品によって7ml~60ml程度と様々な仕様になっています。
ナプキンやタンポンよりも交換の頻度が少なく、長時間使用できることがメリットで、 ナプキンによる蒸れ、かぶれ、かゆみが解消されごわつきもなく快適に過ごせます。
またタンポンのように、トキシックショック症候群(TSS)を引き起こす心配がありません。
使い捨てのナプキンように、石油由来のマイクロプラスチックである高分子ポリマーなどが使用されていないので、デリケートな部分の肌にも環境にも優しく、
洗って繰り返し使用できるので、紙資源の削減、ゴミや海洋プラスチック問題解消など自然環境の保護につながります。
布ナプキン
一般的な使い捨ての紙ナプキンではなく、洗って繰り返し使用できる布のナプキンで、オーガニック素材を使用した、肌に優しい付け心地です。
吸水ショーツのように紙資源の削減、ゴミや海洋プラスチック問題解消など、自分にも環境にも優しく使用できます。
月経カップ(げっけいカップ)
ナプキン、タンポンに替わる生理用品で、タンポンと同じように膣内に挿入して経血を溜めることができます。天然ゴム(ラバー)などの天然樹脂や、シリコーンなどの合成樹脂素材で作られていて、衛生的に消毒して繰り返し使用できます。
従来の使い捨てナプキンの使用を減らして、環境にも優しく使用できます。
月経周期管理アプリ
生理日などを登録すれば、周期や排卵予定日を教えてくれるアプリも注目されています。また基礎体温計を記録して管理できるアプリや、ピルを飲み忘れ防止・オンライン診療で処方を受けられるアプリなどさまざまです。
日本で有名なのは『ルナルナ』。生理日管理ツールのパイオニアで、女性の身体と心の寄り添ったサービスで多くのユーザーに使用されています。
吸水ショーツは、これまでの使い捨てナプキンが当たり前だった生活を大きく変える商品で、漏れを気にしたり、仕事などで交換するタイミングが無い時も安心して過ごすことができます。
また生理がいつ始まるか分からないジュニア世代は、思いがけず生理が始まった場合も、このショーツを身につけていれば安心して過ごすことができます。
ナプキンを取り替える面倒がなく、周囲を気にして生理用品を取り出すこともなくなるので、生理中の不安なストレスから解放されます。
参考:オーガニックコットン製品と布ナプキンメイド・イン・アース さん
生理の貧困とは
さまざまなフェムテックの商品が広まって、女性が抱える悩みが改善されている反面、「生理の貧困」が問題になっています。
「生理の貧困」とは、経済的な理由などで生理用品の購入が困難な状態にあることで、コロナ禍で収入が激減したり、「家庭が経済的に困窮している」、「ネグレクトで生理用品を購入してもらえない」などの声がネットを通じてシェアされたことから、日本だけでなく世界的なムーブメントになっています。

昨年NHKの報道番組で「生理の貧困」実態が報道されて急速に注目されたこともあり、
「生理の貧困」は人の尊厳に関わること、「女性全体にかかわる不平等」として捉えるべきだとの声もあがっています。
声を寄せた人の中には、学生でバイト代が新型コロナウィルスの感染予防のために激減したため、学費と食費を優先させて、生理用品をトイレットペーパーで代用している人もいました。生理中に十分なケアができないつらさは、学びや今後の仕事にも影響し、心の傷や将来の不安につながります。
「生理の貧困」を少しでも解消するために、地方公共団体やNGOなどでは無料でナプキンが配布されるなど、社会全体で「生理の貧困」への取り組みがスタートしていて、ジェンダー平等の観点からも、男女を問わず女性の身体について理解が求められる時代になってきています。
今後は「生理の貧困」を解消するために、繰り返し使用できるフェムテック用品の有効活用も期待されると思います。
出典:NHKクローズアップ現代「生理の貧困 社会を動かす女性たち」
当たり前の日常を見直す
女性は平均で40年間、生理を経験するといわれています。
女性にとってその生理期間は、自分の身体と向き会って、知ることができるとても大切な期間です。
この期間をケアするために、生理中でもいつもと変わらずに安心して快適に過ごせるための商品が開発されています。それは自分だけでなく環境にも配慮した商品です。
環境に配慮したさまざまなフェムテック商品の中には、洗って繰り返し使用する手間がかかるものもあります。
たとえば吸水ショーツや布製ナプキンも使用後に洗う手間があります。
ただこれは自分と向き合うという視点で考えてみると、経血を確認して自分の体調を知ることにもなります。自分の身体をいとおしく思えて、健康で過ごすことに感謝できる時間です。
また、生理は月に1度、5日間ほど出血があり、期間中に20枚のナプキンを消費します。
高分子ポリマーがマイクロプラスチックとして使用されているナプキンで考えると、
1人の女性が9,600枚のナプキンを人生で使う計算になり、
1つのナプキンに含まれるプラスチックの量は、レジ袋4枚分相当といわれ、
女性は生涯で、38,400枚ものレジ袋に値する量を消費していることになります。
経皮吸収率の観点だと、腕の吸収率を「1」とした場合、女性のデリケートゾーンは約42倍の吸収率といわれています。
経皮吸収率の高いデリケートゾーンは、日常使用している製品から化学物質などの有害なものが体内に入りやすく、これは経皮毒といわれていて、体内に溜まると毒素を排出する影響もあって経血が増える傾向にあるとのことです。
ナプキンに使用されている高分子ポリマーも化学物質であり、熱を冷ますシートにも使用されていますので冷えにつながっているかもしれません。
これらの問題はないという意見もありますが、確かな安全性は確立されていません。
長年使用するとしたら、安心して使用できるものを選びたいのです。
豊かな時代になって、便利な商品も多くありますが、当たり前の日常を見直して自分と地球にやさしい選択をしたいと感じました。
最新記事:色のオーダーメイド「特色印刷」で、こだわりを伝えるメリットとは?はこちら
関連記事:【ナプキン・紙おむつ問題】
関連記事:SDGsをわかりやすく!